広報室について
春華堂のブランド価値向上と認知拡大を目的に、SNS運用、企画、プレスリリース配信、メディア対応を担当。商品撮影や広報物制作、社内報作成など社内外への情報発信を統括。「お菓子を通じてお客様に心温まるひとときを提供する」という企業理念のもと、商品の魅力を発信し、地域貢献や新事業展開を支えるコミュニケーション活動を推進している。
メンバープロフィール
高山 慎吾
好きな商品
栗みそまん
入社年
2018年
入社までの経歴
近畿大学経営学部卒業→某広告企業・マーケティング協力部新卒入社→春華堂中途入社
入社後の経歴
営業部(2018~2020)→広報室(2021~)

入社のきっかけ
このまま転職したら、もう二度と故郷には戻らないかもしれない
学生時代、文学や音楽、漫画などの作品の中に、自分の感情の正体を求めていた時期がありました。自分では解決できないモヤモヤを、どこかの誰かが書き留めくれているように感じてスッキリする。また、「なんでこんなの作ったんだろう?こんな時に、こんな気持ちで作ったんだろうな」と想像を膨らませる。そんな人間でした。
キャッチコピーなど、「何かを発信すること」に興味を持ち、大学卒業後に就職したのは東京の広告業界でした。発信することに興味を持って入社し、様々な経験をさせていただきました。同僚やクライアントにも恵まれ、楽しい思い出もありましたが、最終的には営業マンとして、「どれだけ売り上げを立てて、トップセールスマンになるか」という働き方でしたね。
キャリアアップという言葉が流行っていた時代でもあり、都内で転職を考えた時に、「このまま転職したら、もう二度と故郷には戻らないかもしれない」とふと思い、1社くらいは地元でも受けてみようと面接を受けたのが春華堂でした。もっと言うと、妻が勝手に私の履歴書を春華堂に送っていたんです。そんな経緯で臨んだ面接の場で、間宮専務から「浜松を一緒に売り込んでいかないか?」という言葉をいただきました。ただその一言に心を動かされ、入社を決意しました。目先の成果主義だった前職に比べ、春華堂は10年後、20年後に地域をどうしたいか?を見据えている。正直、地元にそんな視点で仕事をしている企業があるとは思ってもいませんでした。創業130年を超える長い歴史のある企業で、一過性のブームではなく、“カルチャーの創造”に関われることに胸が高鳴り、入社を決めました。入社から7年経ち、今の間宮専務は浜松を超え「日本を世界に」とよく言っています。どこまで行くんだろう?そう思わずにはいられませんね。
部署の役割と存在意義
「伝える」というよりも「積み重ねていく」
春華堂の広報とは、メンバーの日々の営みや活動という「事実」を現場に赴いて、丁寧に掘り起こし、それを確かな形にして未来の礎へとつなげていくことです。広報を通して、どう会社を、地域をよくするかが肝心であると思っています。
今の春華堂があるのは、先人たちが長い時間をかけて踏み固めてきた確かな土台があるからこそです。私たちの使命は、その土台の上に新しい時代の春華堂を築いていくことにあります。会社や地域そのものの価値をどう伝え、どう未来に引き継いでいくか。
まさにそこがいま私たちに問われているのだと感じています。よく「挑戦的ですね」と言っていただくこともあります。新しい取り組みができているという意味では前向きな評価かもしれません。でもこれからはもっと「春華堂って、何かやってくれそうだ」と思ってもらえる存在でありたいです。その”期待感”こそが大切だと考えています。以前、新しい企画を立案する際に、過去の例を探して提案したことがあります。すると「今までにない視点を求めてあなたと一緒に働いているのに、意味ない」と叱責されました。その言葉は今も心に残っています。
ちゃんと自分の目で見て、感じて、考えた物事を記録し、残していく。広報の仕事は「伝える」というよりも、むしろ「積み重ねていく」仕事なのだと思います。宣伝のように即効性のあるものではなく、じんわりと伝わっていくものだからこそ、時間がかかる。今取り組んだ施策がすぐに成果につながるとは限らないんです。広告やメディアの仕事に携わってきた身として、この環境は難しくもあり、同時に長い時間軸で価値を育てていける、とても魅力的な仕事だと感じています。

仕事で心が動いた体験
「20年後、30年後もこの場所で商売する」という意思表示
私たちは、思い出を売っている
日本のお土産文化って、世界的に見ても非常に独特なものだと思っています。自分が旅に出させてもらったことへの感謝の気持ちを周りの人たちに伝えるーーー。旅をしている時に、そこにはいない誰かのことを想像するんですよね。「誰に買って帰ろうか、何を選ぼうか」って。これは日本らしい和の精神であり、この文化は結構重要であると感じています。お菓子っていうのは、生きていくために必須ではないけれど、その場にあるとコミュニケーションのきっかけになる。だからこそ、お菓子には文化を媒介する力があるのだと思っています。
入社してしばらく経った頃、国際空港や首都圏エリアの新規開拓を任せていただきました。初めてお取引をさせていただいた関東の大手スーパーマーケット様で、「土用の丑の日企画」としてうなぎパイを販売していただいた際に、お客様のアンケートを拝見する機会がありました。そこには、心に残る言葉がいくつも並んでいました。
「うなぎパイが売られると聞いて、タクシーで来ちゃいました」
「静岡の友人が毎年送ってくれていましたが、数年前に亡くなってしまって…。今日はその方を思い出して食べます」
「若いころは車でよく浜名湖SAなどに行ったけれど、もう免許も返納しました。懐かしくてうれしいです」
そのアンケートを読みながら、胸が熱くなったのを今でも覚えています。私たちは、お菓子だけではなく、そこに紐づく「思い出」を届けているんだなと、その時、実感したんです。だから、安易にパッケージを変えたりすると、その人たちの思い出を無かったことにしてしまうんですよね。もし流行に合わせたポップなデザインにしましょうとなったら、その人たちの大切な思い出はどっか行ってしまう。これが「カルチャーをつくる」ということの本質なんだと思いました。
春華堂は幸せを独占しない
社長や専務がおっしゃる「企業の幸せは、家庭の幸せに似ている」という言葉は特に印象深く心に残っています。どんなに立派な家でも、隣人が不幸であったり、誰が住んでいるのか分からなかったりしたら、その家庭は本当に幸せだと言えるでしょうか。同じように、どんなに自社が順調であっても、隣接する企業や関わる取引先、地域の人々が不幸せであれば、それは真の意味での幸せとは言えませんし、健全な状態でもありません。
春華堂にはそうした考え方が自然と根付いています。たとえば何か事業を起こすときも、春華堂だけが潤うかたちでは、それは幸せとは言えません。地域のお土産として得られたお金は、やはり地域のために使う。資産を投じてオープンしたnicoeやSWEETS BANKも、浜松に新たなランドマークを作ろうという想いと同時に、「20年後、30年後もこの場所で商いを続けていく」という意思表示です。
自分たちだけでなく、関わるすべての人々のことも大切にしながら、情報を伝えていく下地が、春華堂にはあります。単に成果や業績を示すだけでなく、関係する人々の営みや努力、喜びや想いを丁寧に広めていく。それが本当の意味での「健やかな企業の幸せ」につながるのだと思っています。
これから挑戦したいこと
どんな成果が出るかわからない。でも、やり続ける。
春華堂はまもなく140周年を迎えます。この節目に取り組む周年の企画は、単なる記録にとどまらず、春華堂のブランドや街、人々とのつながりを美しく描き出す、「特別な贈り物」にしたいと考えています。
そのために何より大切にしたいのは、自分たちの町が好き、守りたい、なんとかしたいという実感を伴った想いです。私自身、15年ぶりに浜松に戻ってきた当初は「正直、つまんないな」って思っていました。「この町から出たくて出たのに、結局戻ってきてしまった」と。ただ、色んな人と出会って浜松の魅力に触れるうちに、「やはりこの町に恩返ししていきたい」と感じるようになるんですよね。居心地がよくなってきたということだと思うのですが、じゃあ、その心地のいい場所をどれだけ未来に残せるかだと思うんです。
社内においても、春華堂人として「何かの役に立ちたい」と思う気持ちをどれだけ育んでいけるか。それがいまの私の役目だと感じています。
何であれ、始めた当初はどんな成果が出るかなんてわからない。でも、やり続けるんです。例えば、3年前に「和栗を世界に」という想いのもと始まった「和栗協議会」の取り組みも、当初は我々自身も「一体何が始まったんだろう?」と戸惑っていました。しかし今となっては、栗の名産地であるフランスのカンヌやコルシカからお声がかかるようになっています。島国の地方都市でコツコツと積み重ねてきた取り組みが、世界から注目されるなんて奇跡のようじゃないですか。最近では国内のテレビや新聞でも、私たちも深く関わっている「掛川栗」という言葉が取り上げられるようになってきました。
いま栗の苗を植えても、実を結ぶのは早くて3年後、5年後になります。しかし近い将来、製造部は当たり前のように栗の商品をつくり、直営部は当たり前のように販売する。そんな時代が必ず訪れるはずです。だからこそ感謝の気持ちを込めて、「140周年の春華堂、そしてその頃の浜松はこうだった」という記憶と物語を、世代や地域を超えて共有できる”作品”として未来へ残していきたいと考えています。
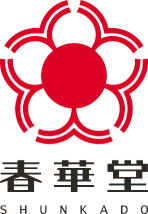

 前の記事へ
前の記事へ

